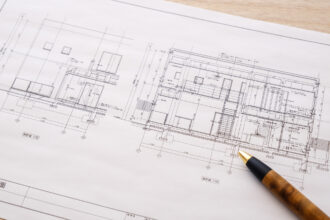公開日 2025.02.26
長期優良住宅の認定を受けるには?
新築の約4件に1件は長期優良住宅!
新築戸建て住宅の長期優良住宅の認定取得率が、令和5年度 31.3%となり4年連続の増加となりました。
長期優良住宅は、ビルダー様にとっては市場ニーズに応えるとともに、品質の高い住まいを提供するための重要な選択肢の一つです。
しかし長期優良住宅の認定を受けるには、ビルダー様として様々な基準をクリアするよう取り組む必要があります。
今回は長期優良住宅の認定基準について解説していきます。
■長期優良住宅(新築)の認定基準
長期優良住宅の認定を受けるためには、次のような認定基準を満たすことが必要です。
①劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
認定基準:住宅性能表示制度の劣化対策等級3相当+追加措置
②耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
認定基準:住宅性能表示制度の耐震等級2・3相当
③維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
認定基準:住宅性能表示制度の維持管理対策等級(専用配管)等級3相当
④省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されれいること。
認定基準:住宅性能表示制度の断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6
⑤可変性(共同住宅・長屋)
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
認定基準:躯体天井高さ 2,650mm以上
⑥バリアフリー性(共同住宅等)
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
認定基準:高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3
⑦居住環境
良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
認定基準:地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。(申請先の所管行政庁に確認が必要)
⑧住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
認定基準:一戸建て住宅 75㎡以上、共同住宅等 40㎡以上(少なくとも1の階の床面積が40㎡以上)
⑨維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
認定基準:以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定
・住宅の構造耐力上必要な部分
・住宅の雨水の侵入を防止する部分
・住宅に設ける給水又は排水のための設備
⑩災害配慮
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
認定基準:災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて所管行政庁が」定めた措置を講じる。(申請先の所管行政庁に確認が必要)
■認定手続きの基本的な流れ
長期使用構造等であるかの確認の申請 登録住宅性能評価機関へ長期使用構造であるかの確認
▽ ・・・約3週間(審査機関による)
確認書等の交付 確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認結果が記載されたもの)の交付
▽
認定申請 所管行政庁へ認定申請・適合審査・認定 ※申請は着工前までに行う必要があります
▽ ・・・約10日間(所管行政庁による)
認定/着工 認定通知書の交付
長期優良住宅は、ビルダー様にとって大きなビジネスチャンスであり、高い品質基準を満たすことで結果として得られる信頼は大きな価値を生みます。
「でも設計・施工に力を入れれば業務量が増加してしまう・・・」 「申請業務に時間をとられるのは・・・」
そんなビルダー様の不安を少しでも解消する手段のひとつとして、設計業務のアウトソーシングという方法があります。
増え続ける設計業務の解決手段として検討してみてはいかがでしょうか。
☆許容応力度計算なら木造構造省エネ計算サポートセンターにお任せ☆
貴社の設計業務量を抑えつつ、耐震性能を担保することができます。
長期優良住宅や設計住宅性能評価取得もワンストップでお任せいただけます。

|
執筆:サポートセンター省エネ室 星野(二級建築士)
外皮計算・一次エネルギー消費量計算を年間100棟以上担当 |
お問い合わせ
お電話はこちらから
025-384-8805